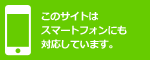フクロモモンガはフクロモモンガ科フクロモモンガ属の哺乳類です。
げっ歯類と思われがちですが、カンガルー等と同じ有袋目でメスはお腹に袋を持ち、育児嚢で子供を育てます。
オスは唾液や臭腺でマーキングします。額や胸に臭腺があり、成熟すると額がはげてきます。
体長16cm~21cm。体重90~150g。寿命は飼育下で10~15年。
飼育の適温は25℃~28℃と言われています。(当店では25℃~30℃で飼育)
フクロモモンガは夜行性で野生下では群れで生活するので、1匹で飼育する場合は飼い主さんが「仲間」となり1日1度は遊んであげてください。
ここから本文です
Menu
フクロモモンガ生態
フクロモモンガの飼い方
高さのあるケージ(SANKOイージーホーム40ハイ以上)・ポーチやハンモックなどの寝床・水差し・エサ入れ・止まり木等・回し車などのおもちゃなどがオーソドックスな飼育用品になると思います。
フクロモモンガは夜行性なので、ケージの置く場所は直射日光の当たる場所は避けるようにしましょう。
ただし、まったく日の光が届かない事も健康上問題なので、間接的に日光の光が入るような場所に置く事をお勧めします。
本来は温暖な地域に生息する動物のため、ある程度の保温(推奨27℃前後)をしてください。
「匂い」で人を覚えるため、慣れるまでは威嚇する子や噛んでしまう子もいますが忍耐強くお世話することで「信頼」してもらえます。
匂いを覚えてもらえるよう、ケージ内に自分の匂いのついた洋服を入れてあげたりポーチ等を首からぶら下げたりして匂いを覚えてもらいましょう。
初めのうち慣れるまでは、無理に触ったり捕まえたりせず様子を見てあげましょう。
無理に触ったり等して「手は敵だ、怖いものだ」と思われないよう気をつけましょう。
個体差はありますが、よく慣れている子は名前も覚えてくれますよ♪
嫌なとき、嬉しいとき、呼んでいるとき等色々な鳴き声があります☆
ジコジコジコ・・・警戒、威嚇など
ワンワン、アンアン・・・仲間や飼い主を呼ぶとき、発情期など
シューシュー・・・不安やイライラしてるとき、ベビーが泣いてる場合は親を呼んでいます
プププ、ククク、プクプク・・・嬉しいとき、満足しているときなど
などがあります。
フクロモモンガの食事
主な食事は果物・野菜・昆虫・樹液などです。
生ものの食事を与える場合は傷みやすい事を考慮し、数時間で食べきれる量を与えましょう。
フクロモモンガ専用フードなどペレットもありますので、それも同時に置き餌として与えると良いでしょう。
与えてはいけない食べ物もあるので、注意が必要です。
お水に関しては、新鮮なものが飲めるように必ず1日1回交換しましょう。
フクロモモンガの病気
【自傷】
自傷は病気というよりも様々な理由によって、フクロモモンガが自身を噛んで傷つけてしまう事です。
原因として外傷などの身体的なものと、心理的なものがあります。
身体的な場合ささいな外傷でも違和感を感じるとそこから噛みはじめてしまいます。
心理的な場合は仲間と思われている飼い主とのコミュニケーション不足、ケージが狭い、騒々しいなどがあります。
口さえ届けばどこでもかじります。毛や皮膚にとどまらず、筋肉組織や骨までかじってしまうことがあります。
予防として、よりよい環境とコミュニケーションが大切です。
相性もありますが、仲間を迎えたり、一緒の遊ぶ時間を作ってあげましょう。
自傷してしまった場合は薬の投与や、エリザベスカラーなどがありますので動物病院へ連れて行きましょう。
【ペニス脱】
性成熟するとオスはペニスを出したり引っ込めたりすることがあります。
長時間出たままになっていると乾燥して戻りにくくなったり、膨れていたり、毛を巻き込んで戻りにくくなったりします。
すぐに戻れば問題ありませんが長時間出たままだと壊死してしまいます。
予防として、すぐ気付いてあげることが大切です。
出たままの場合、綿棒やティッシュを濡らしペニスを湿らせて戻してあげましょう。
戻らない場合や変色、腫れがある時は動物病院へ連れて行きましょう。
【白内障】
水晶体が白く濁り、視力が低下する病気です。
よく知られる白内障は老齢性のもので高齢になると発症しますがフクロモモンガでは若齢性の白内障が見られます。
これは先天性のもので、母モモンガの栄養バランスが悪く肥満していると、その子供に白内障が起きる可能性があります。
治療しても完治はしませんので、繁殖させるさせないに関わらず栄養バランスを考え、適度な運動で太らないようにしましょう。
【代謝性骨疾患】
あまり聞かない病名ですが非常に多い病気です。
骨は身体の成長が止まればそれ以上長く(太く)なりことはありませんが、骨自体は破壊と構築が繰り返され常に新しい骨が作られています。
それがなんらかの理由で新しい骨が作られにくくなり、スカスカな骨になってしまうので骨折しやすくなってしまいます。
原因としてカルシウム不足、カルシウムとリンの不均衡、ビタミンD不足などです。
ケージの上り下りをしなくなったり、手足の麻痺、身体を支えきれず骨が歪んだり、関節が腫れたりしていると危ないです。
予防として、バランスの良い食事が大切です。
成長期、妊娠中、授乳期など特にカルシウムが必要な時期には特に栄養バランスに気をつけましょう。
【低体温症】
体温が下がる事によって引き起こされる症状です。
仮死状態となり、障害が残ってしまったり最悪命を落としてしまうこともあります。
早急にヒーター等で身体を暖め、同時に部屋の温度もあげましょう。
意識が戻れば暖かいモモンガミルクやはちみつ等を舐めさせ、すぐ病院へ連れていきましょう。
脳が低酸素状態になったり臓器不全になったりと、とても危険です。
低体温症にならないため日頃から温度にはお気を付けください。
【皮下の膿瘍】
菌が原因で炎症を起こし、化膿し膿が溜まります。
多いのは口の中から菌などが入ってしまい、頬や顔付近が腫れることが多くみられます。
腫れなど異変に気付けば早急に動物病院へ連れていきましょう。
抗生物質等のお薬でおさまる事が多いですが、ひどくなると全身麻酔で切開手術が必要となる場合もあります。
また繰り返しなる子もいますので完治するまでしっかり病院へ通いましょう。